数日前、生まれてから暦が一回りする還暦を迎えました。
お陰様で体調も良好で、軽やかな気分で節目の時を迎えられたことに喜びを感じます。
誕生日というのはそれまで送ってきた過去を振り返る時でもあります。
今年は元号が平成から令和に換った年、これも本当にお陰様で、平成の時代は、日本では一度も怪我と歯以外でお医者様のお世話になることはありませんでした。
この年齢になると、同年配の訃報はまだほとんど耳にしませんが、持病を抱えていたり大病を患った方は少なくありません。
そんな中、ずっと健康で過ごせたということは、どんなに感謝しても感謝しきれません。
とは言え、還暦という大きな節目を越え、いつか必ずやってくるであろう死というものをより一層身近に感じられるようになりました。
死が一歩自分に近づいてきた様に感じられたのはこれが二度目です。
今から24年前の1995年、阪神淡路大震災とオウムサリン事件があった大変なあの年の三月、愛する母が亡くなり、自分と死との間にある垣根のようなものがなくなった感じがし、死がこれまで以上にリアルに感じられるようになりました。
生きる日々を川の流れに例えるならば、死とはその先にある滝壺のようなものかもしれません。
まだまだ先にあると思っていた滝壺、親の背中の陰になって見えなかったその滝壺が、まだ遠い先にあるとしてもその存在が見えてきたような気がしました。
そしてその年の8月6日、被爆50年を迎えた広島平和公園で見た灯籠流しの灯りに、長い人類の歴史からすると一瞬の瞬きにも満たない儚い人の命が映し込まれているということを、母の死を通して胸で深く理解することができました。

生と死は表と裏の関係であり、生を全うするためには、死と真剣に対峙しなければなりません。
いつか必ずやってくる死に対し、まるでなきもののように目を背けていては、そこに至る生の歩みを実り多きものにすることはできません。
避けることのできない死を受け入れることは、残りの人生の道筋を直視するです。
自分は何度かの臨死体験、母の魂との触れ合いといったスピリチュアルな体験を重ねてきて、死後の世界に対する恐怖はまったくありません。
それとは逆に憧れのようなものがあり、その憧れの世界に気持ちよく行くために、今の人生を悔いのないよう過したい、また過さねばならないとい多少の焦りすら感じています。
ただ死の扉をくぐることには恐れがあります。
それは人間が与えられた生、その生を己の肉体を使って全うしていくために課せられた、一種の業(ごう)のようなものだと思います。
この世からあの世へと移ろう死を、安らかな心持ちで迎える人もいれば、もがき苦しみその死の瞬間を通る人もいます。
誕生もまた同様で、とても安産なこともあれば、大きな痛み苦しみを感じることもあり、いずれにしてもその体験は強烈で、胎内記憶を宿す幼な子の言葉でも、母胎から脱し産道を通る時の記憶は強く残っているようです。
輪廻を繰り返す長い魂の旅路において、やはり肉体の衣をまとい、脱する誕生や死というものは、最も大きく、かつ濃縮した意味や役割を持つものではないかと感じられます。
ここ数日の間、ごく短期間に一親等を三人亡くしたという二人の方のお話を聴きました。
お一人は我が子を死産で迎え、その同じ年に父親と母親を数日違いで見送り、その時に自分の死生観を徹底的に見直す機会を持ち、その時に得たものが今の仕事に対する真剣さにつながっていると語っておられました。
もう一方は、戦時中満州でお生まれになり、終戦と同時に極めて過酷な境遇に晒され、何人かいた兄弟の内の小さな妹二人を亡くし、その後生まれた妹も生後三日で息を引き取られたとのことでした。
その方の場合の一親等とは、その方のお母さんにとってです。
まったく希望の見えない極寒の地満州で、幼い我が子三人を失った母の気持ちとはどのようなものだったのでしょうか、想像することすらできません・・・。

生や死について、これはあまりにも深い問題であり、容易に言葉で語ることはできず、またその言葉を見たり聞いたりしても、その真意を理解することはできないでしょう。
母が亡くなった数年後に、沈没した船がそこで亡くなった乗組員とともに一夜だけ蘇るという大林宣彦監督の「あした」という映画を観ました。

この映画の死者が生前の姿をもって現れるシーンで、亡き母を思い出し、滂沱の涙を流しました。
身近な人の死は、その人の死生観を豊かにしてくれます。
そしてその豊かになった思いを、今現在周りにいる多くの人に傾けることが残された者の課題であり、亡くなった人に対する供養なのだと感じました。
その死について考えるのは、身近な人の死とともに冒頭に書いたように誕生日という節目です。
このたび還暦という大きな節目と二人の方から死生観について深く考えさせられる機会をいただき、以前から読もうと思っていて本棚に置いていた「葬送の仕事師たち」という本を手に取りました。

この本はあまりにも感じることが多く、そのことはまた別の機会に書きたいと思います。
今この時、健康で生きる喜びを感じられること、そして死というものを真剣に見つめることができることに感謝いたします。





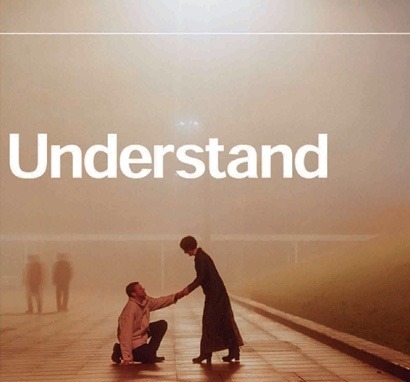




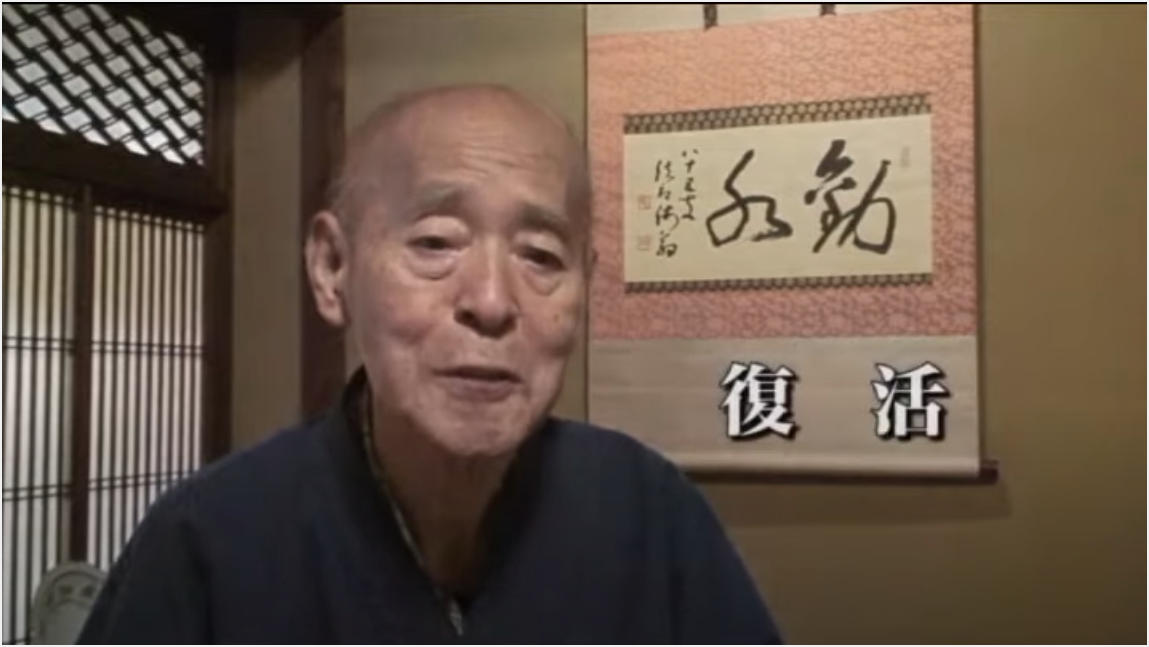

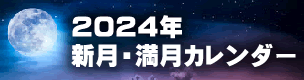


コメントを残す