自分にとって最高の息抜きのひとつが音楽を楽しむこと、そしてその音楽を構成する要素の中でもメロディー、リズム、ハーモニーといった基本要素以前の音そのものに大きな魅力を感じます。
その音とは物理的に解析できるオーディオ的高音質ではなく、そこに表れる演奏者の思い、生き様、そして技量といったものです。
東京医科歯科大学名誉教授の角田忠信先生は、日本人、厳密には六歳まで母語として日本語を使って育った人は、他の言語を使う民族とは大脳の使い方が異なるという研究結果を発表されました。
日本人以外の民族が小鳥のさえずり、虫の音といった自然音を雑音として右脳で処理するのに対し、日本人はそれらを言語と同じく左脳で聴き取り、そこに花鳥風月といったものを感じ取ります。
そしてその聴き取る自然音は、それが何の音か知覚できるような状態だけではなく、ほんの一瞬のパルス音として聞いた場合でも、脳はキチンとそれを聞き分けているというのです。
これは人間の持つ潜在的知覚能力の偉大さを示すものです。

ですから音楽も同様で、音楽以前の音としての状態でそこには様々な情報が含まれていて、それも併せて聴き手は音楽的感動を味わっています。
個々の演奏者が音として伝えるメッセージの多少は楽器の種類によって異なります。
たぶん完全な電子楽器シンセサイザーでもその音に演奏者の内的個性が反映されると考えます。
これは信じる信じないの世界になりますが、植物の超能力を研究されていた三上晃先生は、
「パソコンのキーボードを打つ時にもその人の波動がキーを通してデジタル情報の中に伝わり、そのパソコンで打った文章には作成者の波動が乗っています」
と語っておられました。
これはもちろん現代科学で証明できるものではありませんが、音を通してその感じ方を探っていくと、そういったこともあるのかもしれないと感じます。
けれどやはりその人の波動、生き様が最も伝わるのは、『息は生き』と言うように、呼吸を媒体として演奏される管楽器であり、人の声そのものです。
大きな管楽器を演奏するには大きな肺活量と体力が必要で、演奏家として名高い人のほとんどは男性ですが、その中でもサックスを吹くキャンディ・ダルファーの演奏はひときわ輝いています。
彼女のサックスはまさに音色そのものが実に魅力的です。
何かに例えて表現するならば、野球のバットの真芯にボールが当たり、軽く振ったにも関わらずボールがどこまでも遠くに飛んでいくといった感覚、そよ風のように軽く優しい風が身体の中までじんわりと染み込んでくるような感触です。
つまり音量や音の立ち上がりといった物理的な力ではなく、音の本質そのものが的をピタリと射貫いたストライクであり、そこに力があるのです。
これは人間の身体でいうところの体幹力です。
一流の武道家が軽い力で大男を投げ飛ばすあの力であり、彼女自身、強靱な体幹軸と体幹力を持っているのだろうと推察できます。
このことはずっと以前から感じていたのですが、先日2015年に演奏された「Lily Was Here」という彼女の代表曲を耳にし、その力がさらに極まっていることを知りました。
音そのものに力があるのですから、猛烈に力んで吹きまくる必要はありません。
余裕を持った演奏でギターとのアンサンブルを楽しんでいるといった感じです。
本当に上手い歌手は一番盛り上がるサビの部分で絶叫はしませんね。
それと同じです。
日本にはこの3月に亡くなった異彩のドラマー村上“ポンタ”秀一さんがおられます。
彼は主にスタジオミュージシャンとして活躍していたので知る人ぞ知るといった存在ですが、その卓越した技量に心酔している人も多く、これまでの日本のミュージックシーンを支えてきた重要人物の一人と言っても差し支えありません。
その村上“ポンタ”秀一さんの“伝説”を綴った評論を読み、過去に彼が関わった作品をYouTubeで聞き返してみました。
<スティックを握ってたった4日で…名ドラマー村上 “ポンタ” 秀一の「スゴい伝説」>
このポンタさんの伝説は実に面白く、彼の音楽の本流を貫く生き様がリアルに伝わってきます。
ご一読をお勧めします。
郷ひろみ・沢田研二・キャンディーズ・ピンクレディー・山下達郎・矢沢永吉・泉谷しげる・井上陽水・桑田佳祐・ドリカム……ほか、錚々たるアーティストのサポートを務め、レコーディング総数は、なんと1万4000曲以上! もっとも多忙だった時期は、朝から深夜まで3時間ごとに都内のレコーディングスタジオを移動する殺人的なスケジュールをこなしていたという。
少し(かなり?)懐かしい当時の歌を聴いて驚きました。
どの楽曲も実にパワーが漲り、一瞬にしてあの当時の記憶が蘇ります。
『歌は世につれ世は歌につれ』
この言葉、このホームページで何度も書いたことがありますが、歌謡曲全盛だったあの頃は日本全体が好景気に浮かれた上昇気分で、それが楽曲の中にあふれています。
今でも日本に歌謡曲とか流行歌といったジャンルがあるのでしょうか。
そう感じさせてしまうほど、今の日本の音楽シーンは勢いを失っています。
『記録ではなく記憶に残る』と言われたキャンディーズの歌は久し振りに聴いて特に痺れました。
まさにもぎたての果実を目の前に持ってきて、むいた果汁が頬に飛び散ってきたような鮮烈さを陳腐なパソコンのスピーカーから感じます。
この「春一番」のドラムも村上“ポンタ”秀一さんです。
もう理屈抜きで心臓をわしづかみにするようなパッションは、発表された当時1976年の日本の力そのものですね。
三人の声がピタリと揃ったユニゾンの中に個々の個性を感じさせ、そのバランスが実に見事です。
「微笑がえし」も素晴らしいです。
キャンディーズの歴史を知ってる人にはデビュー当初からの歴史を刻んだ歌詞は感動ものです。
これら楽曲から四十数年、日本の精神文化はとても前に向かって進んできたとは言えません。
「エセ・コロナ禍」で政府、メディアに簡単に洗脳されてしまう今の日本人に必要なのは、あの当時の日本人が持つ力強い生き様ではないでしょうか。
キャンディーズの力強くも美しい歌声を通し、そのことを強く感じます。

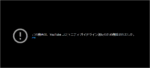










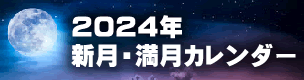


コメントを残す