人は通常死を考える時、「死にたい」と表現します。
これは死と対極の生を実感として持っている人の言葉であり、幼い頃に親からの虐待を受け、生きてきた実感を持ったことのない人は、死の願望を「消えたい」と言うのだそうです。
虐待を受けて育った人たちは、他の普通の人たちとはまったく異なった世界を生きていて、「消えたい」というこの本は、そういった人たちの生き方や幸せについて書かれています。

人間は社会的動物であり、その社会性は幼少期の健全な家庭環境の中で培われます。
けれど社会の中で正常な関わり方をしてこなかった彼らは自我を十分に育てることができず、それゆえに自分という存在が不確かであり、普通の人間だと当たり前のものとして意識することのない感覚を常に見続けなければなりません。
明らかに虐待を受けて育ったにも関わらず、その過去の事実を認識できずにいる人がいます。
過去の記憶がほとんどなく、その流れにある未来を思うことができない人もいます。
ある主婦の方は知的障害がないにも関わらず、曜日や日にちという感覚がまったくありません。
これは幼い頃虐待によって常に緊張を強いられ、夜もゆっくり休むことができず、睡眠による一日の区切りという感覚を身に付けずに育ったことが原因です。
元被虐待児の治療は、一般的な心理療法が適合しないことが多いそうです。
幼少期からの記憶に意識を向け、それを深く見つめることによって家族や他人との関係を改善していく内観という手法がありますが、これを虐待を受けた人が受けると、過去の強烈な苦しみがぶり返したり、虐待した親を愛せない自分に葛藤するそうで、元被虐待児とそうでない人との間には、深くて暗い大きな溝があります。
普通の子どもは家庭や学校で、家族や社会との関わり方を学んでいきますが、元被虐待児の方たちの事例を知ることで、その当たり前と思っていた幼少期の過ごし方の大切さと意味をあらためて感じました。
この本は、人間として社会的に生きる上で身に付けるべきもの、根源的生のすぐ上にあるものを、一般の哲学書や心理学書とは異なった角度から深く教えてくれます。
自分は幼少期に親とどのような関わり方をしてきたのだろうか。
それが今の自分にどのような影響を与えているのだろうか。
これまでほとんど考えたことのない深い部分を見つめ直すきっかけを与えてもらいました。
多くの元被虐待児を見てきた医師である著者によると、内部に異質なものを抱える彼らは独自の発想を持ち、人の真似のできないクリエイティブな仕事をし、偉大な詩人、画家、政治学、デザイナー、小説家といった大きな業績を挙げている人が多いのだそうです。
先の「利己的遺伝子」の考え方によると、この児童虐待もまた生物としての何か意味ある生存戦略なのだと考えられます。
だからと言って、児童虐待による不幸な子どもたちを放っておいていいという訳ではありません。
人間に与えられている課題は、その意味を知った上で、生物的、社会的により多くの人たちが幸せに暮らせる道を探ることだと考えます。
この世は陰陽合い乱れた混沌とした社会です。
ひとつの絵に描いたような理想があって、それに100%の人が適う生き方を求められている訳ではありません。
例えるなら、それはLGBTの人たちを異常だとして排除するようなものです。
児童虐待もまた、人間が社会や家庭というものを作ることによって必然的に生まれた“歪み”、あるいは“あだ花”のようなものだと考えます。
だからこそそれを『絶対悪』とするのではなく、それが生まれた生物的、社会的意味合いを考えた上での対処が必要だと考えます。









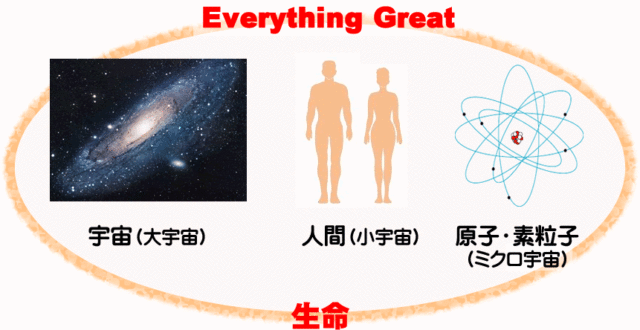

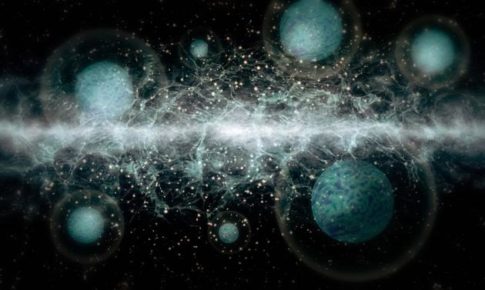

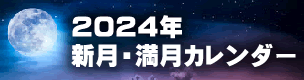


コメントを残す