目が見えず耳も聞こえないという重いハンディキャップを抱えながら、高い学位と豊かな教養を身に付け、生涯を社会貢献活動に費やしたヘレン・ケラーは心から尊敬できる人物です。
彼女の偉大すぎる足跡、そこに少しでも近づきたいと願い、自分の名刺の裏面に彼女の名前を記しています。

先日外で昼食をとった際、何気なくスマホを触るとネットにつながりません。
その直前に誤って機内モードのボタンをクリックしていたのが原因だったのですが、その時は分からず、代わりとしてスマホに保存している電子書籍Kindle本にアクセスしました。
そして開いたのが「ヘレン・ケラー ――行動する障害者、その波乱の人生」、この本を読むのは四年ぶりです。

ヘレン・ケラーの生涯を知ると、人間は努力すれば不可能なことなどないのではないかという気持ちになってきます。
そして今この瞬間、健康な状態で生きていること、自由にどこにでも行けてどんなものにでも見たり聞いたり触れ合ったりすることができること、そこに無上の感謝の思いが湧いてきます。
盲聾という閉ざされた世界にいて、高い知識と教養を身に付けたという事実は人智を超えたまさに奇跡であり、実際に彼女の自伝には『奇跡の人』というタイトルが付けられています。
この本は感動なくして読むことはできません。
そして多くの人に読んでもらいたいと思い、これまでこの本を何冊も買って知り合いにプレゼントしてきました。

けれどこのタイトルの“奇跡”とは、ヘレン・ケラーのことではありません。
音と光、そして言葉の世界から遠ざかっていた当時7歳であったヘレン・ケラーに言葉を教え、生涯に渡ってヘレンのサポートをし続けたアン・サリバン先生のことなのです。
『千里の馬は常に有り、名伯楽は常に有らず』
(一日に千里を駆け抜ける能力のある名馬はいつでもいるが、その才能を見いだす人物はいつもいるとは限らない)
以前勤めていた公文教育研究会の創始者である故公文公氏がいつもこの中国の故事を引用し、教室の指導者の方たちに努力をうながしていました。
サリバン先生はまさにこの名伯楽、極めて優秀な指導者であったことは間違いありません。
またサリバン先生は全盲ではないものの幼い頃から視力に障害があって盲学校に通っていたこともあり、ヘレンの苦しみがよく理解できたのだと思われます。
そして自らの意思を徹底して貫き、家族の反対にあっても一度決めた指導方針は絶対に崩さない頑固で意地っ張りと評される一途があり、盲学校を最優等の成績で卒業した明晰な頭脳も理想の教育をする大切な要因だったのだと思われます。
それでもなお、驚嘆すべきはヘレン・ケラーの努力と能力です。
それがどれほどのものであったのか、想像すらできません。
彼女は1歳9ヶ月の時に高熱を発し光と音を失いました。
その後5歳までに約60の表現動作を身振り手振りで行ったとされていますが、彼女自身9歳でサリバン先生と出会うまでは「毎日が『厚い霧』で覆われていた」と言うように、言語世界からは遠く離れたところで暮らしていました。
それがサリバン先生と出会い厳しい指導の下、あの有名な「water…」と物に名前があることを知るようになり、その後わずか3ヶ月でいくつかの動詞を含む300個以上の単語を覚え、簡単な文章をサリバン先生の手に指文字を使って伝えることができるまでになりました。
最も言語能力が発達する幼少期を閉ざされた闇の中で暮らし、言葉の存在を知ってからも指文字を唯一の手段として飛躍的に言語世界を広げていったことはまさに神がかりとしか思えません。
ヘレンは病に冒される以前の生後6ヶ月目にすでに片言で喋り始めていたというのですから、飛び抜けて高い言語的素養を持っていたことは事実でしょう。
天はヘレンに高い言語能力と極めて重い障害という相反する二つを与え、人類に希望と可能性を知らしめる役割を託したのだと感じます。
ヘレンは指文字からはじまって声の使い方を学び、点字を習得するとともに当時欧米に5種類あった点字法の統一にも尽力しました。
語学も日常使う英語だけではなくラテン語、ギリシャ語、フランス語、ドイツ語も学び、最終的にはラドクリフ・カレッジという、まだ男女の教育差別のあった時代のハーバード大学の女子部を優等な成績で卒業します。
元々持って生まれたのか障害によって習得したものかは分かりませんが、これだけのことができたというのは、サヴァン症候群の人たちのように一度触れたものを写真のように正確に記憶、理解する特異な集中力と記憶力、それに近いものを持っていたのではないかと思われます。
ヘレン・ケラーの生き様の中で特に興味を引かれるのは、こういった高い知的能力習得とともに、限られた感覚器官の中で、どのように世界と触れあってきたのかということです。
健常な人間が周りの環境から受ける情報収集、特に言語などの知的なものは、圧倒的割合で視覚と聴覚に頼っています。
その重要な器官が閉ざされたヘレンがどのように他の器官を使い、また補完作用としてその器官を発達させていったのか、そこに人間が本来持っている大きな可能性を見ることができます。
両腕を持たないサリドマイド被害者の方たちは、脚を手のように使って字を書き、包丁を握って料理を作ることができます。
それに類する並外れた能力を、ヘレンは残された感覚器官の中に身につけていたのではないかと考えます。
人間の持つ五感の中で触覚以外の四感は頭部に集中し、触覚だけは全身を包んでいて別格の存在です。
これは手の指は親指と他の指が対比するように配置されているのと同様で、東洋の五行思想では触覚、親指は地表を覆う土の理であり、統合の理合いだと説かれています。
視覚は網膜に刺激を受けて感知し、聴覚は鼓膜と側頭骨、嗅覚は鼻腔粘膜、味覚は舌といった具合に、視覚以外の四感も広義にはすべて触覚の延長と見ることができます。
視覚と聴覚に障害を持つヘレン・ケラーが、全感覚を統合した“肌感覚”でこの世界をどのように感じ取ったのか、本の中にはこのような記述があります。
「触れるということはヘレンにとって特別なことでした。
手や体に軽く触れるだけで友だちや知り合いを見分けることができました。
音や運動が引き起こす空気の振動や床の振動を正確に区別したともいわれます。」
外界の情報は、目と耳だけで入手すると思い込んでいる人たちがいる。
そういった人たちは、私が歩くだけで、都会の通りと田舎の道の違いを区別できることに驚く。
もちろん舗装の有無だけではない。
彼らは、私のからだ全体が周りの状況を知覚していることを忘れているようだ。
うす暗い地中に閉じ込められた木の根は
地上で梢(こずえ)が受ける喜びを分かち合い
太陽の光、広々とした大気、鳥たちを想像することができる
だから私も、自然の共感によって、同じ行いができるのだ
この豊かな感受性は、まさに“恵み”と呼ぶにふさわしいものだと感じます。
健常な肉体を持つ人間は、このあふれるような恵みに溺れてしまい、本来持っている恵みの尊さを見失っているのかもしれません。
ハンセン病で視力を失い、指先の感覚をも奪われた近藤宏一氏は、聖書の中にかすかな希望を見出し、鉄板に書かれた点字を舌で追って聖書を血で染めたと言われています。
同じくハンセン病であって詩人の志樹逸馬は、
「生きる味に尊厳さがあり」
と語りました。
生きがいは「感じる」ものであって「味わう」もの、
五感や外からの刺激を超え、真の恵み、喜びとは、己の内から湧き上がってくるものではないのでしょうか。
このたびはスマホの不調からヘレン・ケラーの足跡と再び触れ、言葉にできない、言葉を超えた大きなものを受け取りました。
これは自らの内なるものが求めたものである、そう感じ、しっかり味わいたいと思います。

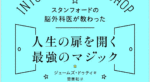





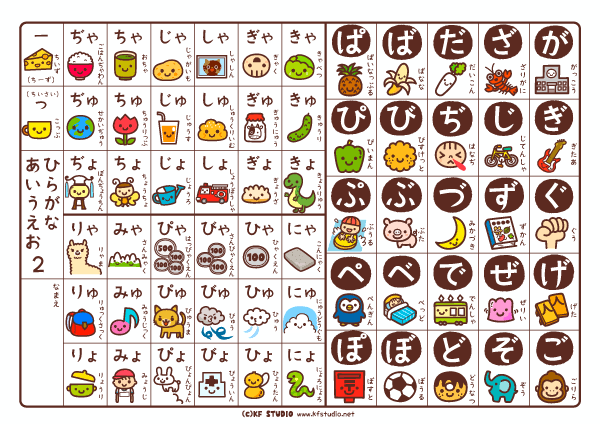




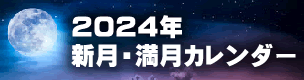


コメントを残す