恍惚としたお年寄りが描かれる時、必ずそのお年寄りの口元は開いた状態になっています。
口元を閉じる力は意志力であり、また自分自身を律する脳の力の表れです。
ここインドでも、口元を鍛えるパタカラとペコぱんだは欠かせません。

舌の筋肉を鍛えるペコぱんだは、始めた当初から五段階強度で最も強いHを使っています。
最初は舌先でドームをへこます動作はかなりハードで、数回行っただけで顎から舌の筋肉がだるくなっていたのを覚えています。
あれから数年、今はその動作を何回でも続けてできるので、毎回百回ぐらいのところで適当に切り上げるようにしています。
そのペコぱんだの影響でしょうか、舌の先にほんのわずかなピリッとした違和感を覚えます。
あまりハードにやりすぎて舌先を傷付けたのかもしれません。
昨日は精読、多読について書き、その舌先の感覚から、今日は味読という言葉が頭に浮かびました。
味読とは「内容や文章をよく味わいながら読むこと」です。
昨日の文章の最後に、
> 食べ物はよく噛んでしっかりと味わいましょう。
> 読書もそれと同じです。
と書きましたが、これがまさに味読ですね。
味読という言葉には、精読以上に感覚的なもの、思い入れが込められているように感じます。
味わいながら読む、そこで頭に浮かぶのは、ハンセン氏病を患い、視力と指先を失いながらも、残された舌と唇の感覚を使いながら聖書や自ら率いる楽団のために楽譜を読み込んでいった近藤宏一さんのことです。

「近藤宏一と青い鳥楽団」というサイトに、そのことが書かれています。
近藤宏一のすぐれた指導力の基盤には、文字通り血のにじむ努力をして獲得した、「舌読」と「点字譜」の技術があった。「青い鳥」結成まもないころ、愛生園に「盲人会」が組織され、「点字講習会」が行われた。近藤ははじめ聖書を読みたい一心で、この講習会に参加した。指先に感覚はなくとも、唇と舌をつかって点字を読む方法があることを、すでに知っていた。全12名の受講生のうち、近藤とともにもう一人の楽団メンバーが、この技術の修得に励んだ。
起きてから寝るまで、食事と治療と楽団の練習時間以外は、すべての時間を、点字の練習にあてた。点字は6つの点ですべての文字と数字をあらわす。その点を唇と舌でまさぐっていく。あまりに集中しすぎて、唇の皮膚が破け舌先がただれて、点字本が血で染まってしまうほどだった。三カ月も過ぎたころには、点字本を一冊(森鴎外の『高瀬舟』だった)、読破することができるまでになっていた。萎えた指に天筆を包帯でくくりつけて、文字を打つこともできるようになった。
上に書かれているように、近藤さんが舌を使ってまで読みたいと願ったのは聖書との出合いがきっかけです。
「私は聖書をどうしても自分でも読みたいと思った。しかしハンセンで病んだ私の手は指先の感覚が無く、点字の細かい点を探り当てる事は到底無理な事であったから、知覚の残っている唇と、舌先で探り読むことを思いついた。」

自分はこんな思いをして本と触れたことがあるだろうか・・・そう感じざる得ません。
近藤さんが自らの血で染めながら読まれた「高瀬舟」を、自分も一ヶ月ほど前に読みました。
点字本を舌でではなく、無料でダウンロードした電子書籍をスマホを使ってです。

致し方ない事情で弟の自殺を幇助してしまい、その科(とが)で縄をかけられ、遠島へ送るために高瀬川を静かに流れる舟の中での情景を描いたこの作品を、近藤さんはどんな思いで読まれたのでしょう。
味読、そこには精読とは違う、読むものに対する愛着、敬愛のようなものが感じられます。
今は何でも簡単に手に入る時代で、ものの有り難みを感じる感覚が鈍くなっています。
例えば音楽分野で三十年以上前まで主流だったレコードは、そこに針を落とすたびに盤面が削られ、いやが上にも聴くたびごとに思いをかけざる得ませんでした。
それが今は音楽でも本でもネット情報でも使い捨ての消耗品のようになっていて、それが結局受け手側の心を貧しくしているように感じます。
断捨離で手元に残すもの、精読するに値する大切な本、これらは自分にとって価値のあるものです。
だから価値のあるものは手元に置き、それ以外のものは手放します。
これはとても効率的ですが、唯物的であり、あらためて考えるととても違和感があります。
自分はこの世のすべてのものに生命があると感じています。
たぶんこの文章を読んでくださっている多くの方も同様だろうと信じます。
「人は価値があるから生きている」のではなく、
「生きていることに価値がある」
これは12年前に初めてインドの児童養護施設を訪ねた時に子どもたちから教わったことです。

その価値というのは人間だけではなく、本でも音楽でも、すべてに通じているはずです。
味読とは、自分にとって価値があるなしではなく、それを作った(創った)人、そのものに対して敬意を払い、そこに存在とともにある価値を感じ、書かれているものを受け取るということではないのでしょうか。
点字本がどのような行程を経て作られるのか分かりませんが、かなりの手間と労力がかかっていることは間違いないでしょう。
近藤宏一さんはそのことも感じながら、きっと一文字一文字味わうように読まれていたのでしょう。




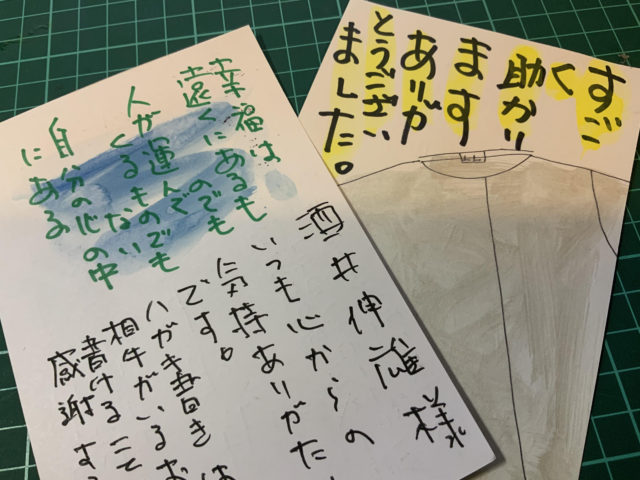
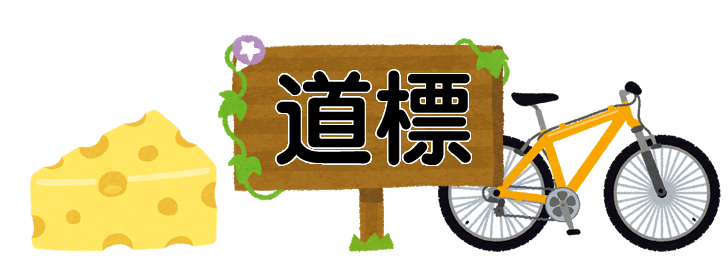




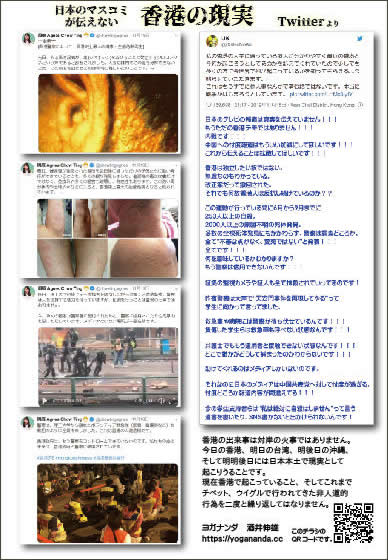

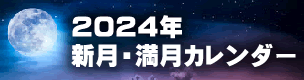


コメントを残す